「国際科学技術コミュニケーション論」第7回講義を実施
2023年12月14日(木)13:52
電気通信大学において、12月1日に今学期第7回目の講義が実施されました。BHN桑原基金寄附講座は、今学期も十分なコロナ対策を実施したうえで、本来の対面授業とオンラインのハイブリッド形式にて開講されています。
今回の講義は「国際技術連携・技術支援の活動」というテーマで、山下 孚(まこと)講師(BHN会長)と渡辺 栄一講師(BHN参与)の二人の講師により行われました。教室での対面授業では12名の学生が聴講しました。

電通大の講義教室での対面授業の様子
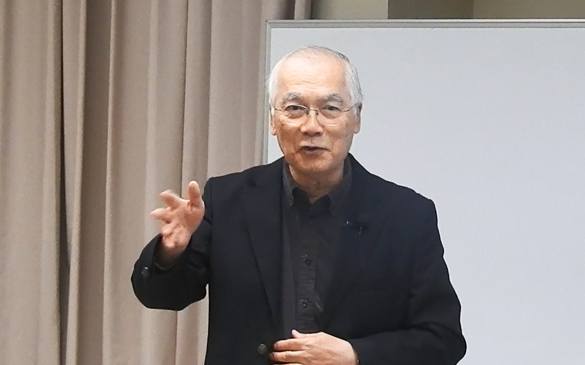
ODAに関する歴史や活動の目的・内容等を講義する山下 孚講師
山下講師の講義では、ODAの歴史や日本におけるODAの主な機関とその活動の動向や、現状について、 ODAの活動におけるNGOの存在やNGOに期待すること、NGO団体としてのBHNの団体概要や支援活動についての話がありました。
講義は最初に以下の質問が学生に向けて投げかけられ、それについて多くの図やグラフを用いながら行われました。
Q1:What come to your mind when you hear the term “International technical cooperation and/or support?”
Q2:Please give examples of “International technical cooperation and/or support.”
Q3:Why do you think we need to cooperate and give support internationally?
Q4:Do you know how many foreign students are there in Japan now?
Q5:Do you know how many Japanese students are studying abroad?
日本のODAの特色である「人材育成」の事例紹介で前半の講義を終え、青年海外協力隊などで支援活動経験のある渡辺 英一講師が紹介され、後半の講義へとバトンタッチされました。

海外支援活動について講義する渡辺 栄一講師
渡辺講師からは日本のODA活動として、青年海外協力隊で実際ケニア、インドネシアやミャンマーで行った活動が豊富な写真や動画を用いて時系列的に紹介されました。
特にミャンマー ラカイン州グア郡学校及び村落における防災支援および保険衛星意識向上支援事業の動画では、毎年自然災害が発生しているという部分では、学生からは「うわぁ~」という驚きの声も聞こえました。防災・減災や保健衛生でBHNの支援活動が多くの人々に役立っていることがこの動画から知ることができました。
そして、最後に余話として、ミャンマーに長期滞在中に早朝のヤンゴン人民公園をウォーキングし、現地での友達も出来、また健康管理もできてダブルでメリットが有ったという経験談もありました。
最後に国際協力活動の教訓として、以下のことを挙げました。
・現地の人々の立場に立ち、現地の文化、習慣、価値観を尊重し、現地のコミュニティのために働く
・現地の視点からニーズ(実際と潜在的)を理解する
・結果よりもまず信頼を得ること
― あなたの会社やあなた自身のためではなく、その国(地域)のために ―
終了時には学生たちから拍手を受け講義は終了しました。
