「国際科学技術コミュニケーション論」第7回講義を実施
2025年11月18日(火)15:12
10月3日(金)からスタートしている後学期の授業科目 「国際科学技術コミュニケーション論」 の7回目となる授業が、11月14日(金)に電気通信大学(以下、電通大)で実施され、対面とオンラインによる授業形式で進められました。 今回の講師は「国際技術連携・技術支援の活動」というテーマで、山下 孚 (まこと)講師/BHN会長 により行われました。

電通大キャンパス東門側 新C棟403号教室
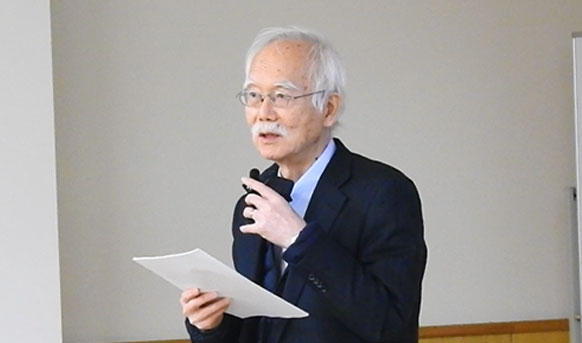
由良 憲二電通大名誉教授からの紹介でスタートしました
■第7回講義 : 国際技術連携・技術支援の活動 山下 孚講師/BHN会長
山下講師の講義では、まず、はじめに
・「国際技術協力・国際支援」と聞いて何を思い浮かべますか?
・なぜ国際的に協力し、支援する必要があると思いますか? (あなたがその必要性に同意したと仮定して)
という2つの問いからスタートし、国際協力・支援の重要性やその方法等が話されました。
その後、ODA(Official Development Assistance = 政府開発援助)とは何か?という切り出しから、ODAの概要や日本のODA のスタートは第二次世界大戦後の補償からで、その後、経済的影響を受けながら、2023年の開発協力大網の改訂に至ったという歴史と日本のODAの役割が話されました。
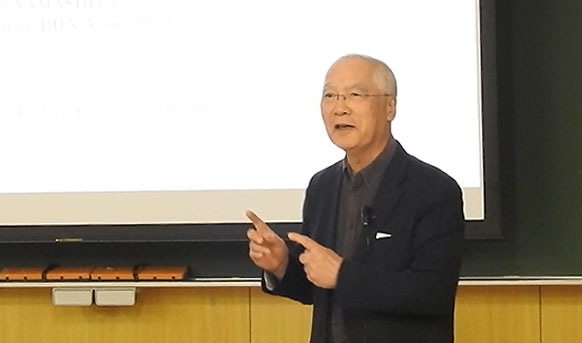
ODAに関する歴史や活動の目的・内容等を講義する山下講師
また、海外の国際開発協力支援機関・団体組織として、USAID(U.S. Agency for International Development)やKOICA(Korea International Cooperation Agency)等の紹介があり、日本における国際協力団体として、JICA国際協力機構(Japan International Cooperation Agency)の概要及び、JICA の使命や目的等について説明されました。
次に「人材育成」というテーマで、1954年のコロンボ計画に参加し、日本初の政府開発援助として開始して以降、日本は開発途上国での指導的役割を担う技術研修生を受け入れ、最先端技術から村おこしのノウハウまで、様々なテーマでの専門知識や技術を提供していることや、途上国(または国際機関)からの個別の要請に基づいて、国連の開発援助活動としての技術協力専門家の派遣も行われていることが紹介されました。
なお、日本の専門的な知識や技術を用いて支援を行なう代表的な技術支援団体として、青年海外協力隊(JOVC)、シニア海外協力隊(SVOC)の紹介を、エピソード:青年海外協力隊の誕生とJ・Fケネディ大統領の演説(アメリカ平和部隊)を交えて話されました。
講義の後半では、交換留学について「海外からの在日留学生の数(2024年5月)」、「海外における日本人留学生の数(2024年3月)」といった2つの質問をし、それについて図やグラフを用いながら解説をし、解説の中では、若者の留学促進への取り組みとして【J-MIRAI(Japan-Mobility and Internationalization)】を紹介し、日本のモビリティと国際化:次世代への再挑戦と加速への取り組みについて話されました。
尚、上記2つの問いに関する答えは、在日留学生:336,708人、海外への日本人留学生:89,179人でした。

講義に対して質疑応答をしている場面
最後にNGOとNPOの違いと、日本のNGO事業に対する無償資金協力やジャパンプラットフォーム(JPF)等、支援活動への資金協力の仕組み、そして、NGO団体であるBHNの団体概要や「将来の ICT リーダーのための BHN人材育成プログラム活動」の紹介、国際標準化活動についての説明等をし、終了時には学生たちから拍手を受けて今回の講義は終了しました。
