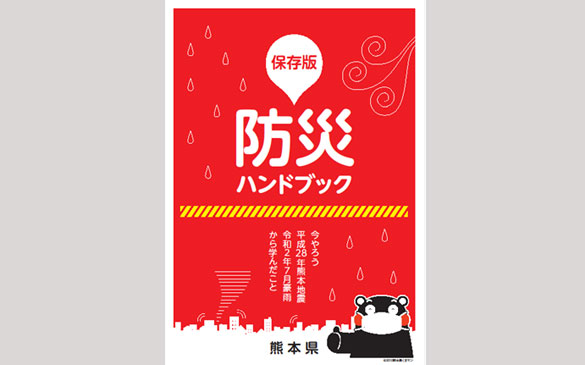国内災害ICT支援活動拠点ネットワーク事業~熊本事務所の取り組み、益城町木山下辻団地で防災・スマホ研修会~
2024年1月30日(火)14:43
BHN熊本事務所(所長 色見 高司氏)は、2016年4月に発災した熊本地震被災地(熊本市、益城町、嘉島町、御船町、甲佐町、西原村、南阿蘇村等合計7市町村)おいて、復興フェーズ毎に(避難所フェーズ 6カ所、仮設住宅団地フェーズ 47カ所、災害公営住宅団地フェーズ 9カ所)、各種の工夫を取り入れた「ICTを活用した地域コミュニティ再生・活性化支援活動」を実施してきました。熊本地震被災者支援事業
BHN熊本事務所では、益城町木山下辻団地よりICTを活用した支援活動の継続要請を受けました。「国内災害ICT支援活動拠点ネットワーク事業」において、支援活動の継続要請に積極的に応えつつ、併せて、①熊本事務所の事業継続及び近接地域で発生する新しい国内災害へ即応体制の維持、②地震災害被災者支援事業で獲得した各種経験・ノウハウのデジタル資料化、③南海トラフ巨大地震及び首都直下地震等に備える「既得通信機材を利活用する広域災害後方支援ICT機能整備」等を進めていきます。国内災害ICT支援活動拠点ネットワーク事業
2023年12月15日(第6回 防災・スマホ教室)及び2024年1月19日(第7回 防災・スマホ教室)の開催模様を報告します。
2023年12月15日、「第6回 防災・スマホ教室」、熊本県益城町木山下辻団地、住民4人、講師はBHN熊本事務所の色見 高司氏、井嶌 都氏、吉田 和子氏、楠本 邦昭氏が担当しました。この日のテーマは「熊本県が作成している防災ハンドブック等を活用したICT防災学習(続き)、スマホの各種活用法」を行いました。
●防災ハンドブック等を活用したICT防災学習「最新の防災情報を入手する」
前回に引き続き、「熊本県作成の防災ハンドブック」を教材として活用しました。「最新の防災情報を入手する(P23~26)」をTV画面に映し、みんなで話し合いました。更に、「熊本県作成の防災ハンドブック」を各自のスマホに取り込んで、確認しながら討論を続けました。色見 高司氏が講師を担当しました。
bousai02.pdf (pref.kumamoto.jp)
◆画像をクリックするとPDFが開きます◆
●「熊本県 統合型防災情報システム」の紹介
続けて、熊本県 統合型防災情報システムを紹介しました。
パソコン版「熊本県 統合型 防災情報システム (pref.kumamoto.jp)」を説明しました。
●スマホの取り扱い練習「はがきデザインキットを利用して年賀状の作る方法」
スマホの取り扱いについて様々な要望が寄せられました。この日は、「はがきデザインキットを利用して年賀状を作る方法」を指導しました。井嶌 都氏が講師を担当、自身のスマホ画面をTV画面に写して、受講生の理解度を上げながら説明しました。

「熱心な受講生の皆様、進歩を実感」
(2023年12月15日撮影)
2024年1月19日、「第7回 防災・スマホ教室」、熊本県益城町木山下辻団地、住民6人、講師はBHN熊本事務所の色見 高司氏、井嶌 都氏、吉田 和子氏、楠本 邦昭氏が担当しました。この日のテーマは「熊本県が作成している防災ハンドブック等を活用したICT防災学習(続き)、スマホの各種活用法」を行いました。
●防災ハンドブック等を活用したICT防災学習「備えて安心 非常持出品と備蓄品」
色見講師と井嶌講師は、いつもの講義に先立って、最初に「自由討論会」を開催しました。2024年度計画について希望を確認しました。是非、引き続き研修を継続してほしい強い要望が寄せられました。

色見講師、井嶌講師「最初に自由討論会」
(2024年1月19日撮影)
前回に引き続き、「熊本県作成の防災ハンドブック」を教材として活用し、「非常持出品と備蓄品(P27~28)」を説明して、みんなで話し合いました。色見氏が講師を担当しました。
いざ、急いで避難しなければならないとき、何をどれだけ持っていくか、とっさに判断できるものではありません。非常持出品は日頃から用意しておきましょう。

色見講師、「防災ハンドブック、非常持出品と備蓄品」を説明、討論
(2024年1月19日撮影)
●「災害用伝言板(web171)」研修
井嶌講師は災害用伝言ダイヤル(プッシュ式電話機用)、災害用伝言版(携帯電話用)について説明しました。

井嶌講師、吉田講師「本日学習した内容を個別質問に答えています」
(2024年1月19日撮影)

旧仮設益城町役場庁舎跡地は、公民館等複合施設として開発中
(2024年1月19日撮影)
旧仮設益城町役場庁舎跡地は、公民館等複合施設として開発中でした。
理事(プロジェクトマネジャー)
有馬 修二