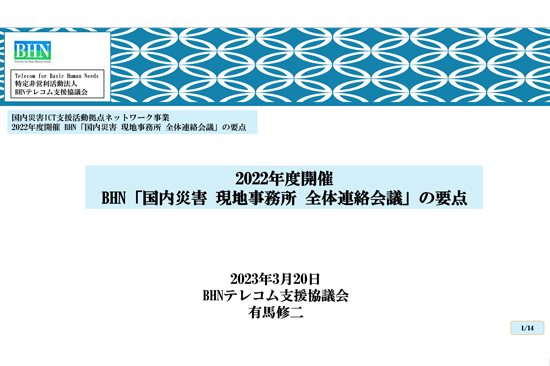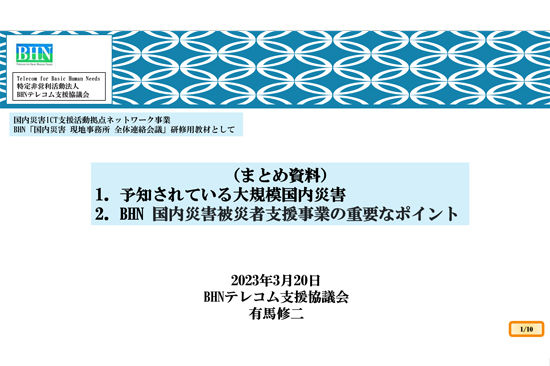国内災害ICT支援活動拠点ネットワーク事業~2022年度 国内災害 現地事務所 全体連絡会議の開催状況~
2023年3月24日(金)16:23
2011東日本大震災以来、日本各地で大規模な国内災害が頻発しています。南海トラフ巨大地震及び首都直下地震等の大規模広域災害の発生も予知されています。一方、多くの経験・ノウハウを獲得してきたBHN国内災害被災者支援事業が次々に終了時期(2011東日本大震災宮城被災者支援事業・2019年3月末終了済、2016年熊本地震被災者支援事業・2023年3月末終了予定、2018年西日本豪雨被災者支援事業・2023年3月末終了予定)を迎えました。
BHNテレコム支援協議会では、新たな国内災害に備えるため、①既設現地事務所の事業継続及び近接地域で発生する新しい国内災害へ即応体制の維持、②被災地域毎・災害種類毎・支援活動毎に特徴ある既存事業で獲得した経験・ノウハウのデジタル資料化、③南海トラフ巨大地震及び首都直下地震等に備える広域災害後方支援機能の整備等を目的として、2019年4月よりBHN自主事業「国内災害ICT支援活動拠点ネットワーク事業」を開始しました。

国内災害ICT支援活動拠点ネットワーク事業
国内災害ICT支援活動拠点ネットワーク事業 | BHNテレコム支援協議会 (bhn.or.jp)
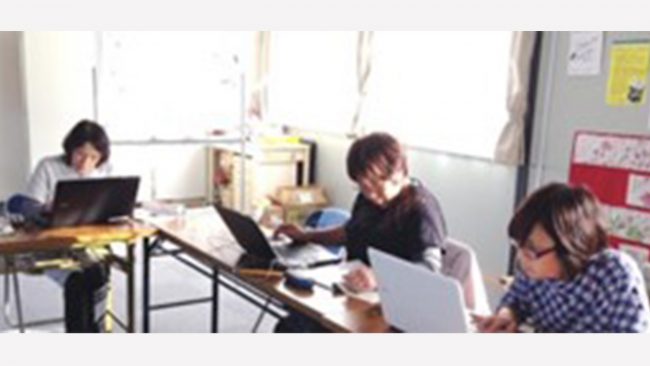
東日本大震災 宮城被災者支援事業
東日本大震災 宮城被災者支援事業 | BHNテレコム支援協議会 (bhn.or.jp)

熊本地震被災者支援事業
熊本地震被災者支援事業 | BHNテレコム支援協議会 (bhn.or.jp)

九州北部豪雨被災者支援事業
九州北部豪雨被災者支援事業 | BHNテレコム支援協議会 (bhn.or.jp)

西日本豪雨被災者支援事業
(含む、令和3年7月・8月豪雨被災者支援活動)
西日本豪雨被災者支援事業 | BHNテレコム支援協議会 (bhn.or.jp)
BHN自主事業「国内災害ICT支援活動拠点ネットワーク事業」に関する、上記①の考え方に基づき、2019年4月以降に発災した規模の大きな国内災害には、個別事業を立ち上げて被災者支援事業に取り組みました。具体的には、2019年度には令和元年台風15号・19号被災者支援事業、2020年度には令和2年7月豪雨被災者支援事業、2021年度には令和3年7月・8月豪雨被災者支援活動等を、それぞれ宮城、熊本、広島の各既設現地事務所を基点とする個別事業を立ち上げ実施に移しました。尚、令和3年7月・8月豪雨被災者支援活動は西日本豪雨被災者支援事業に包含して取り組みました。

令和元年台風15号・19号被災者支援事業
令和元年台風15号・19号被災者支援事業 | BHNテレコム支援協議会 (bhn.or.jp)

令和2年7月豪雨被災者支援事業
令和2年7月豪雨被災者支援事業 | BHNテレコム支援協議会 (bhn.or.jp)
2016年熊本地震被災者支援事業及び2018年西日本豪雨被災者支援事業が1年後に終了する新たな段階に備えて、上記➀、②、③の考え方を一歩進める取り組みとして、2022年4月より毎月一度「ネットを活用した国内災害 現地事務所 全体連絡会議」を開催しました。
三つの現地事務所の皆さまがネットを介して相互交流する「場」を設けて、宮城事務所、熊本事務所及び広島事務所の各々がこれまでに獲得してきた「経験・ノウハウのデジタル資料化」及び「既得通信機材を利活用する広域災害後方支援機能の整備」について話し合いました。
尚、「既得通信機材を利活用する広域災害後方支援機能の整備」では、三つの現地事務所の皆さまがそれぞれの被災地において、これまで実際に活用してきた通信機材(パソコン・プリンター・タブレット・スマホ・ポケットCO2センサー・ドコモおくダケWi-Fiアクセスポイント・home5G/SH-52Wi-Fiルータ・各種ネットサービス)をブラシュアップして、南海トラフ巨大地震及び首都直下地震等の大規模広域災害の発生に備えて、「広域災害後方支援機能のための整備と活用ノウハウの獲得」を目指して、取り組みを継続していきます。
(画像をクリックするとPDFが開きます)
第1回(2022年4月18日)
はじめに「国内災害ICT支援活動拠点ネットワーク事業のねらい」を確認し、新しい国内災害等への備え、経験・ノウハウをデジタル資料化、拠点間をネットワーク化、新しい国内災害、南海トラフ巨大地震及び首都直下地震等に備える等について、討論しました。
第2回(2022年5月23日)
「いなむらの火」を取り上げて、経験・ノウハウをデジタル資料化し、伝えつづけることの大切さについて、討論しました。
第3回(2022年6月20日)
「スフィア・ハンドブック」を取り上げて、人道憲章と人道支援における最低基準、 CHS:人道支援の必須基準(9つのコミットメント)、そして「説明責任」、ワンペーパー、HPを活用した積極的な広報活動等について、討論しました。
第4回(2022年7月26日)
災害時及び平時からの支援活動連携 ~全国及び県単位中間支援組織の役割~について、討論しました。
第5回(2022年8月23日)
安全対策(交通安全対策、安全作業対策、新型コロナウィルス感染防止対策等)について、討論しました。
第6回(2022年9月27日)
知識創造への挑戦1「経験・ノウハウのデジタル資料化」及び各事務所の知識創造への挑戦について、討論しました。
第7回(2022年10月25日)
知識創造への挑戦2「日本国の全ての防災・減災情報及び対策のワンページ化」、及び各事務所の知識創造への挑戦について、討論しました。
第8回(2022年11月21日)
予知されている大規模国内災害(その1) 南海トラフ巨大地震、及び各事務所の知識創造への挑戦について、討論しました。
第9回(2022年12月19日)
予知されている大規模国内災害(その2) 首都直下地震、及び各事務所の知識創造への挑戦について、討論しました。
第10回(2023年1月23日)
予知されている大規模国内災害(その3) 千島海溝・日本海溝巨大地震、及び各事務所の知識創造への挑戦について、討論しました。
第11回(2023年2月20日)
予知されている大規模国内災害(その4) 地球温暖化・海面上昇・スーパー台風・高潮災害、及び各事務所の知識創造への挑戦について、討論しました。
第12回(2023年3月20日)
まとめ(1)「日本国の防災・減災、国土強靭化対策状況」
まとめ(2)「自由討論」~自然災害を乗り越え、持続可能な社会実現に、我々は何ができるか!~について、討論しました。
新たな国内災害、予知されている大規模国内災害等に備えるため、3現地事務所(宮城、熊本、広島)の皆さまと一緒に繰り返し確認した内容を「BHN 国内災害被災者支援事業の重要なポイント」としてまとめました。
(画像をクリックするとPDFが開きます)
予知されている大規模国内災害
➀南海トラフ巨大地震
➁首都直下地震
➂千鳥海溝・日本海溝巨大地震
➃地球温暖化・海面上昇・スーパー台風・高潮災害
BHN 国内災害被災者支援事業の重要なポイント
(1)国内災害に対するBHNの基本方針
(2)国内災害ICT支援活動拠点ネットワーク事業の狙い
(3)経験・ノウハウをデジタル資料化し、拠点間をネットワーク化し、
新しい国内災害、大規模国内災害・南海トラフ巨大地震及び首都直下地震等に備える
(4)高い確率で予知されている南海トラフ巨大地震、首都直下地震等に備えて
既存事業で獲得した経験・ノウハウのデジタル資料化、広域災害後方支援ICT機能整備等
(5)広域災害後方支援ICT機能の整備・検証・実践
(6)BHN HPを活用した積極的な広報活動
(7)BHN(Basic Human Needs)とは?
(8)国内災害ICT支援活動拠点ネットワーク事業(2023年度~テーマ)
(画像をクリックするとPDFが開きます)
2023年度から、BHNテレコム支援協議会の3現地事務所(BHN宮城事務所長:石垣 正一氏、BHN熊本事務所長:色見 高司氏、BHN広島事務所長:福田 卓夫氏)では、新たな国内災害、予知されている大規模国内災害等に備えるため、引き続き、①既設現地事務所の事業継続及び近接地域で発生する新しい国内災害へ即応体制の維持、②被災地域毎・災害種類毎・支援活動毎に特徴ある既存事業で獲得した経験・ノウハウのデジタル資料化、③南海トラフ巨大地震及び首都直下地震等に備える広域災害後方支援機能の整備等に、地道に取り組んでいきます。
尚、2023年3月に終了する、熊本地震被災者支援事業、西日本豪雨被災者支援事業(含む、令和3年7月豪雨・8月豪雨被災者支援活動)等の各被災地から引き続き寄せられている支援活動継続要請には「国内災害ICT支援活動拠点ネットワーク事業」に組み入れて実施していきます。
熊本地震被災者支援事業
西日本豪雨被災者支援事業
(含む、令和3年7月豪雨・8月豪雨被災者支援活動)
プロジェクトマネジャー(理事)
有馬 修二